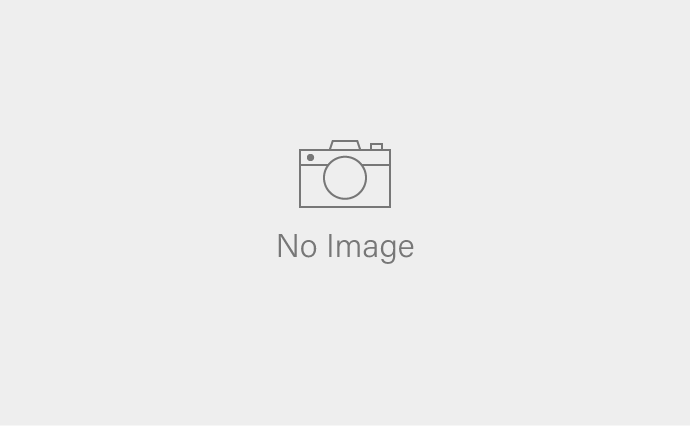先日書いた消防設備士甲種第4類の記事の需要があるようでしたので、乙種第6類についても記事を作成することにしました。
これから乙種第6類の受験を考えている人のために、合格までの流れを解説します。
【資格概要】
消防設備士の第6類は主に消火器に関する資格です。
消火器は日常のあらゆる場所で使用され、需要が多いこともあり、消防設備士の中で最も受験者が多いです(公式の統計情報)
また、消火器は購入のみで対応が可能で工事をする必要がないため、乙種しかありません。
甲種は学歴や他資格の取得など、受験するために条件があるのに対し、乙種は誰でも受験可能なため、受験のハードルが低いことも、受験者が多い一因でしょう。
【試験科目】
試験科目については、筆記試験と実技試験の二つに分かれています。
筆記試験:「消防関係法令」、「基礎的知識」、「構造・機能・整備」
法令は共通部分と、第6類特有部分の2つに分かれています。乙6以外の消防設備士の資格を所有している場合には、共通部分は免除となります。
実技試験:「鑑別」
鑑別等では写真を見て名称や用途を問う問題が出題されます。甲種と違い、自ら作図をすることはありません。
【合格基準】
筆記試験において、各科目毎に40%以上で全体の出題数の60%以上、かつ、実技試験において60%以上の成績を修めた者を合格とします。
なお、試験の一部免除がある場合は、免除を受けた以外の問題で上記の成績を修めた方を合格とします(公式サイト原文引用)
筆記試験で合格基準を満たしていない場合、実技は採点されないそうです。
【勉強時間・勉強方法】
受験した当時は仕事が忙しかったのもあり、かなり直前になって勉強を始めました(3週間ほど前くらい)。
平日は1日1時間、土日は5時間ほど勉強して、トータルで50~60時間ほどの勉強時間だったと思います。
使用したテキストはナツメ社のものですが、写真やイラスト付きで非常にわかりやすかったです。章ごとに理解度確認テストがあり、そこで自分がまだ覚えていない場所を確認できるので、勉強が進めやすい印象です。
法令については周回を重ねて暗記するしかありません。基礎的知識については大学で材料力学などを受講した方はほとんど勉強しなくてすむでしょう。
構造・機能・整備については、消火器の分類、加圧の方式を理解したうえで、各消火器の構造やパーツを覚えましょう。鑑別の章では実物の写真があるので、そちらと交互に勉強すれば理解がより深まると思います。
その他には、薬剤の種類、点検方法も覚える必要があります。
鑑別については、少なくとも消火器を見てなんの種類か、各消火器がどのような構造になっているかは理解しましょう。
個人的には筆記側とかなり内容が被るので、そこまで力を割かなくても大丈夫な印象ですが、油断しないようにしましょう。
【参考書】
参考書はナツメ社のテキストを使用しました。
公論出版の方は使用しませんでしたが、甲4など他種のテキストも評判が良いため、そちらでも問題ないと思います。
以上です。記事をお読みくださりありがとうございました。
この記事が合格の一助になれば幸いです。
下記にて他の資格についても概要を載せております。興味のある方はぜひ見てください。