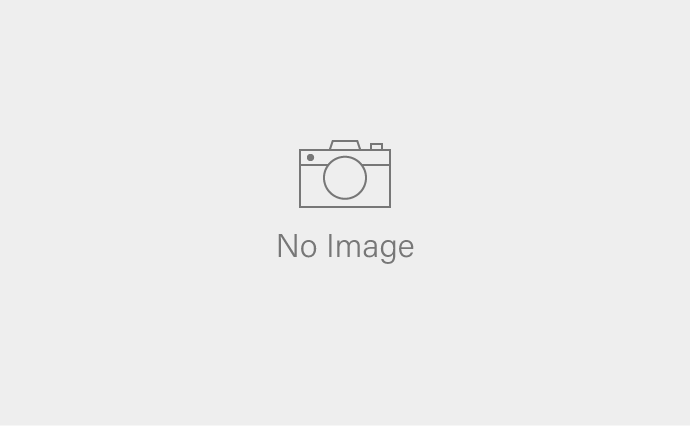こんにちは。くそねみです。
6月になりましたが、エネルギー管理士を受験される方はそろそろ勉強を意識し始める時期ではないでしょうか?
エネルギー管理士は科目合格制度があるため、数年かけて合格を目指す人もおられるかと思いますが、手間や費用を考えると一発合格をするに越したことはないと思います。
本記事では管理人がどのようにして一発合格したかを解説していきます。
【資格概要】
「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に基づく省エネルギー関係の資格です。
一定以上のエネルギーを使用する工場では、使用量に応じてエネルギー管理者を選定しないといけないため、今後も一定数の需要が見込まれます。
試験日は基本的に毎年8月上旬(第1日曜日が多い)です。
【試験科目】
科目は「エネルギー総合管理及び法規」、「熱と流体の流れの基礎」、「燃料と燃焼」、「熱利用設備及びその管理」の4つとなります。
科目合格制度を採用しているため、3年間の間に4科目全てに合格すれば取得することができます。
法規以外の科目については、大学レベルの知識が必要になってきますので、各科目それなりに勉強が必要です。
大学、大学院で化学工学系の方は「熱と流体の流れの基礎」は比較的取りやすいと思います。
また、ボイラー関係の資格を既に取得済みの方や、普段の業務で携わっている方であれば、「燃料と燃焼」の科目は比較的楽に点数を取れると思います。
【合格基準】
合格基準は各科目とも60%です。労働安全系の資格と違い、得意な科目を得点源とすることはできません。
【勉強時間・勉強方法】
管理人は6月に入ってからは平日は1日1時間、休日は3時間ほど勉強時間を確保するようにしました。使用した参考書は、テキストを1冊と過去問を1冊です。
法規については、テキストを読んだ後に、過去問を解いて間違えた箇所を再度周回してつぶしていくという形で勉強しました。
熱と流体の流れの基礎については、個人的には4科目の中で一番難易度が高く、勉強時間を費やしました。テキストを読み込むのはもちろん、過去問を解いていて理論がわからない部分については、大学自体に使用していた化学工学、物理化学の本を読みなおし、理論を理解するように努めました。
また、次元計算で解法を思い出したりするので、ぱっと見でわからない問題についても、最後まで諦めずに解いてみると、意外といけたりします。
(管理人はラスト5分前に解法を思い出して、気合で埋めました)
燃料と燃焼については、燃焼計算を間違えないこと(たまに酸素や窒素が分子内に入ってきて間違えやすい)、各燃料(気体、液体、固体)の燃焼方式を記憶しておけばおおよそ問題ないでしょう。
ボイラー技士の試験では、エネ管よりもう少し簡単な燃料、燃焼に関係する問題が出てきますので、エネルギー管理士の受験前にボイラー技士を受けておくと少し楽になると思います。
熱利用設備及びその管理については、計測および制御、熱利用設備と出題範囲が広いです。熱利用設備については必須回答が2問と選択回答で2問となります。
選択問題については、自分の業務に関連して解きやすい問題をあらかじめ決めておくと楽でしょう。初見の方、ボイラー技士等のボイラー関係の資格を既に取得されている方は熱交換器、工業炉、熱設備材料の3つが比較的楽かと思います。
【参考書】
以上です。記事をお読みくださりありがとうございました。
このブログが合格の一助になれば幸いです。
下記にて他の資格についても概要を載せております。興味のある方はぜひ見てください。