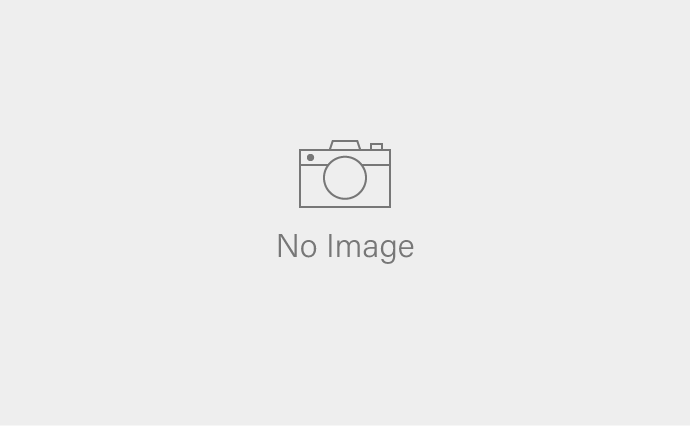本記事では化学メーカーで働くのにおすすめの資格を紹介します。
「必須」、「あると便利」、「任意」の順に分け、それぞれの資格の概要や所感を記述しています。
管理人が持っている資格については勉強法など個別記事を作成します。
【必須】
①危険物取扱者 甲種
消防法に関連する資格で、化学メーカーに入ったら最初に取得する可能性が最も高い資格。
危険物(特に4類の引火性液体)の取り扱いができるようになる。
危険物施設の改造する場合には変更届などを所轄の消防へ提出する必要があるため、その辺の知識も習得できる。
必須に挙げている資格の中では酸欠作業主任者の次に簡単だと思われる。
②高圧ガス製造保安責任者 甲種化学
高圧ガス保安法に関連する資格。
試験内容は方法としては「学識」、「保安管理技術」、「法令」の3つに分かれており、5月ごろに行われる検定に合格すれば、11月に法令を受けるだけですむので、可能であれば検定を受けることをお勧めする。
甲種については記述式のため、難易度は危険物と比較して高い。一方で大学で物理化学を受講していれば、その知識で解ける問題も多い。
爆発などの安全工学に関わる問題も出るため、その範囲については新たに覚える必要がある。
エネルギーの使用の合理化等に関する法律に関する資格。
科目は「エネルギー総合管理及び法規」、「熱と流体の流れの基礎」、「燃料と燃焼」、「熱利用設備及びその管理」の4つ。
科目合格制度を採用しており、3年間の間に4科目を合格すれば取得することができる。
大学時代に化学工学、物理化学を受講していれば、「熱と流体の流れの基礎」および「燃料と燃焼」は解きやすい。
また、「熱利用設備及びその管理」については選択問題であり、自分の業務に関わる内容を選択すれば比較的楽。
④公害防止管理者 1種水質
公害防止管理者は大気と水質の2つを挙げているが、1科目目の「公害総論」は共通科目であり、公害防止管理者の初回受験者は水質は5科目、大気は6科目を受けることになる。
そのため、水質を先に受けることで大気の科目数を1つ減らすことができる。
1種水質の固有科目は「水質概論」、「汚水処理特論」、「水質有害物質特論」、「大規模水質特論」の4つ。
中の人は24年に受験予定。
⑤公害防止管理者 1種大気
1種大気の固有科目は「大気概論」、「大気特論」、「ばいじん・粉じん特論」、「大気有害物質特論」、「大規模大気特論」の計5つ。
「公害総論」を他の区分で合格していない場合、6つの科目を受験することになるため難易度が上がる。
個人的には内容が普段触れることがない「大規模大気特論」が一番難しかった。
他の科目については職場に電気集塵機やバグフィルターなどがあれば理解しやすい印象。
この資格については講習を受講し、最終日に行われるテストで6割以上の点を取れば取得可能。
そのため、難易度は必須に挙げてる資格の中で最も簡単。
一方でタンクや蒸留塔への入槽の際に、内部の酸素濃度を測る必要があり、自分で持っていると便利。
死亡事故に繋がることが多い、酸欠作業の基礎知識を習得することができるため受けておいて損はない。
【あると便利】
・有機溶剤作業主任者
・特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者
職場の労働安全に関わる資格。難易度はそこまで高くない。
科目は「労働衛生(有害業務に係るもの)」、「労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの)」、「労働生理」、「関係法令(有害業務に係るもの)」、「関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)」の計5つ。
各種作業主任者を取得していると、そこで学んだ知識が流用できるため、少し難易度を下げることができる。
管理職にならない限りは必要ないと思うが、どこかで取得した方が良い資格。
・ボイラー技士:2級解説
労働安全衛生法に基づいた、ボイラーに関する資格。
2級、1級、特級とあるが、取り扱うだけならばどの級でも可能(作業主任者になるには伝熱面積に応じた級が必要)
免許の交付に実務経験が必要になるため、上位の級の取得を考えている場合は早めに取得した方が良い(1級の交付には2級取得後2年、特級の交付には1級取得後5年の実務経験が必要)
・統計検定
【任意】
・石綿作業主任者
古い工場の場合、未だに石綿含有の保温が残っていたりすることがある。
ここ数年で法改正があり、調査の義務化があったため、知識として持っておくと便利かもしれない。
・公害防止管理者 ダイオキシン
・QC検定
・機械保全技能士
・自主保全士